ビジネスで成功するために必要なものは…「実力」or「運」それとも…???
本屋にいくと、いろんな本のタイトルが目に飛び込んできます。
本のタイトルのつけ方って、すごく上手なのでコピーライティングの参考になりますね。
その中でもひときわ「ん???」と目を引いたのが、本書です。
タイトルもストレートでそそられるし、装丁もなんとも挑戦的でワクワクします。
本の購入は、ネットの評判、Amazonのレコメンド、メンタリストDaigoさんのおすすめ(笑)、そのあたりからセレクトして買うことが多いのだけど、年に何冊かはいわゆる「ジャケ買い」してしまいます。
この本もその「ジャケ買い」のうちの1冊です。
ジャケ買いした本はかなりの確率で「ハズレ」を引くのだけど(僕の選定能力の低さ…)、この本はなかなか面白かったので、記事にまとめたいと思いました。
著者の紹介
著者は「ふろむだ」さんです。
Amazonから著者の紹介を引用します。
ふろむだ
のべ数百万人に読まれたブログの著者。多様な業務経験を活かして、主に仕事論などの記事で人気を博す。リアルでは複数の企業を創業し、そのうち1社は上場を果たす。ポストとしては、平社員、上司、上司の上司、上司の上司の上司、取締役、副社長、社長を経験。業務としては、プログラミング、設計、仕様定義、企画、マーケティング、採用、アートディレクションなどを経験。『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』が初めての著書となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
Amazonより引用
ふろむださんの初めての著書が本書のようですね。ブログの世界でも活躍されている方です。
ペンネームで出版されている理由は、本文に記載してありますので、そちらを参考に。
人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている本の読みやすは?
正直にいってしまうと、めっちゃ読みにくかったです。
文字も大きくて、図表やイラストがたっぷり入っていて、余白も多い。
これだけ見ると読みやすそうな印象なのですが、実際に読んでみると、どこか取っ散らかっているような紙面構成になっていて、どこに何がどの順番で書いてあるのかが分かりづらい。
僕のように、章立てをみつつ、読み飛ばしたり、熟読したりと読書スピードを調節しながら読むタイプには向かない構成でした。
ただ、内容が分かりにくいか、といえば決してそうではなく、事例もたくさん書かれていて楽しく読むことはできます。
文字ばかりの本は見ただけで読む気が失せる、、、というタイプの人には読みやすいと思います。
本書の要約
この本の要約として、マインドマップを作りましたので参考にして下さい。
(使用ソフト:X-mind)

まとめるとこんな感じ。
要約を一言でいうと
「相手に出来るヤツと思い込ませたら勝ち」
という内容でした。
本書を読み解く上で重要な3つのキーワード
この本の中に書かれていることで、重要なキーワードを3つピックアップします。
キーワード:その①
「錯覚資産」
人は本当に実力があるかどうかよりも、実力があると思われることが重要だということです。
本当に実力があっても、そう思われなければ上司からの評価も低いままだし、良い仕事のチャンスも巡ってこないのです。
逆に、実力は大したことが無くても、「有能だ」と思われれば、周囲の評価も高く良い仕事を与えられるチャンスも増えていきます。
これが長く続いたらどうなるでしょう?
A:実力はあっても閑職にしか付けず、大きな仕事をさせてもらえないままでいた人と、
B:実力は大したことが無くても、大きな仕事をバンバン経験させてもらって経験を積んだ人。
AとBの10年後を想像してください。
実際に仕事の実力はどちらがついていると思いますか?
おそらく、Bの方が実際の実力も上回っているのではないかと思います。
つまり、「有能だ」という錯覚を与えることによって、真の実力もついていくということなんですね。
本書の中ではこの「錯覚」のチカラのことを「錯覚資産」と表現しています。
実力があるように見せけると、チャンスに恵まれ、実力は後からついてくる。
そしてさらに「あの人は有能だ」という錯覚が大きくなっていく。
錯覚の度合いのことが錯覚資産ということになります。
資産というぐらいなので、どんどん溜め込んでいけるわけです。
仕事上の成功なんて、ほとんどの場合「運」で決まったりするのですが、これを「運」ではなく、「実力」と思い込み、また思い込ませることが錯覚資産を増やしていくポイントです。
キーワード:その②
「ハロー効果」
ここでいう「ハロー」というのは「後光」のこと。
後光がさすとその者が光り輝いて見える、ということからつけられているようです。
ハロー効果とはどういうものかというと、何か1つ良いことがあると他のことも良く見えるし、逆に何か1つ悪いところがあると他のことも悪く見えるということです。
これ、よくありますね。
例えば、いつも真面目な人がたまたま遅刻した場合と、いつもだらしない人がたまたま遅刻した場合、どちらが許してくれやすいか。
いつも真面目なほうですよね。
たまたま遅刻したという事実は同じなのに。
もう1つ例を出します。
事業で大成功を収めた経営者が考えた新しいアイデアと、事業で失敗して会社を倒産させた元経営者が考えた新しいアイデア。
仮に全く内容が同じアイデアだったら、どちらが世の中に受け入れられやすいでしょうか?
答えは明白ですね。
これもアイデアそのものは同じですけど、誰が考えたかが「ハロー効果」によって歪曲させられているのです。
イケメンが言った甘い言葉と、ブサメンが言った甘い言葉。
どちらも同じ言葉だったとしても、受け取り方は違いますよね(笑)
このように、何か1つ秀でたものがあると、他もいいと思ったり、すごく見た目が良いと、その人が言った言葉に賛同しやすかったりといったことが起きます。
自分はそんなことない。偏見は無い。と思っている人。そういう人が一番無意識に「ハロー効果」を実践していることもあり得ますよ。
キーワード:その③
「認知的不協和」
これは、ちょっと怖いなぁ、と思いました。
認知的不協和というのは、人間は自分の矛盾や葛藤を解消するために認識や記憶を勝手に書き換えるというもの。
例えば、自分が買ったものが思いのほか使いづらくて良くなかったとします。
それが、高額商品で何か月も働いて貯めたお金をつぎ込んで買ったものだとしましょう。
本当なら、「使いにくくて最悪だ」という評価=認識になるのが妥当ですよね。
実際に自分でもそう思っているのですから。
でも、それでは一生懸命お金を貯めた苦労が報われないという矛盾が生じます。
その時に、人は勝手に「これはこれでいいところもあるのでアリだな」という認識にすり替えてしまうのです。
これが「認知的不協和」です。
本書の内容をビジネスに役立てるポイント
実力のあるフリをする
本当に実力があるかどうかは関係なく、実力のあるフリをするといいです。
成績が優秀な先輩のように振る舞う、やたら小難しい本をいつも読んでいるところを見せつける、専門用語を駆使して煙に巻く。
そういったことでもいいので、とにかく人に「あいつひょっとしたら大物かも!」と思わせたら勝ちです。
見た目に気を配る
人は見た目で判断します。
ハロー効果を狙うなら、スーツはパリッとしたものを着て、髪型はさわやかに、身に着けているものもこだわりのブランド品を、靴はピッカピカに磨き上げる。
人は見た目じゃないよ!
そう言いたいのは分かりますが、錯覚資産を築くためには、見た目のハロー効果は大事です。
ヨレヨレのボロボロでは、誰も「あいつに仕事を任せよう」とは思ってもらえません。
まとめ
人は思い込みで生きているけど、思い込みだとは気が付かない。
ならば、その思い込みを利用してビジネスの世界で成功していくのも立派な「戦略」だと思います。
同期のライバルがドンドン出世していってしまったという人も、本当の実力はあなたの方があるのかもしれないです。
ならば、すぐに錯覚資産の構築をはじめて、ライバルを追い抜いてやりましょう!
そんな人に、本書はおすすめです!
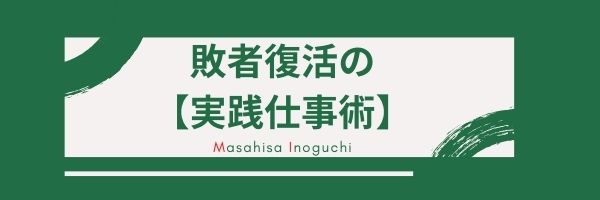
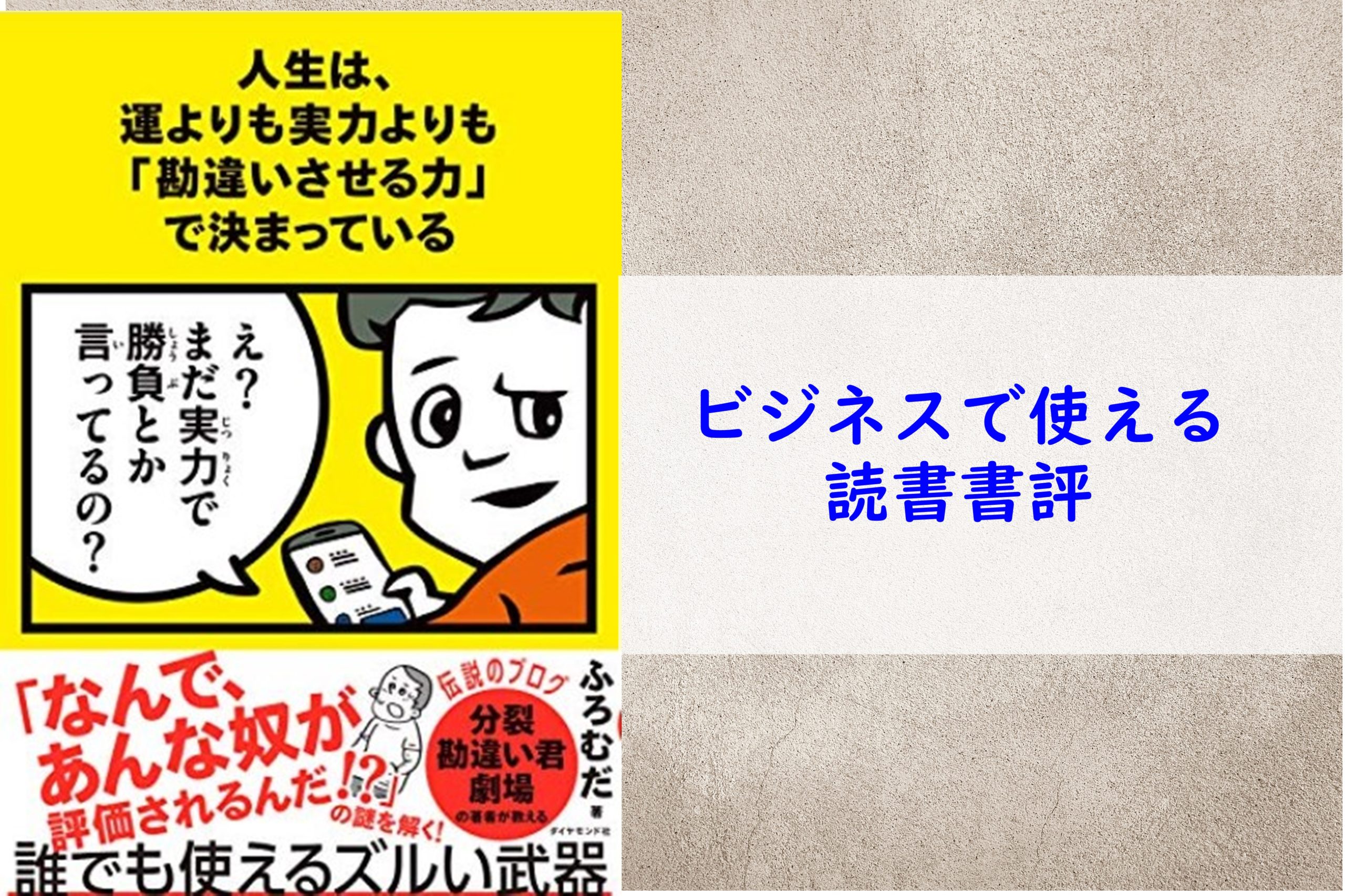


コメント